先日、江南市の小学校でゲスト講師としてお招きいただき、2年生に「どうぶつのお医者さんってどんなお仕事?」というお話をしてきました。
国語の授業で「どうぶつ園のじゅうい」を学んだ子どもたち。
教材を通じて動物との関わりや獣医師の仕事に興味を持ってくれたようで、「獣医さんのお仕事について直接お話を聞けるよ!」と先生から聞くと楽しみにしていてくれたとのこと。
自分も子どものころから動物が好きでしたが、動物にもお医者さんがいるなんてことを知ったのは中学生になって犬と暮らすようになってから。
言葉の通じない動物の診療を通じて人との絆に関わる仕事に魅力を感じたのでした。
今回はなんだか珍しい存在に思われがちな獣医師の仕事を子どものうちから身近に感じてもらい、困りごとや違いに目を向ける意識を子どもたちにお伝えしたく、このような機会をいただくことができました。
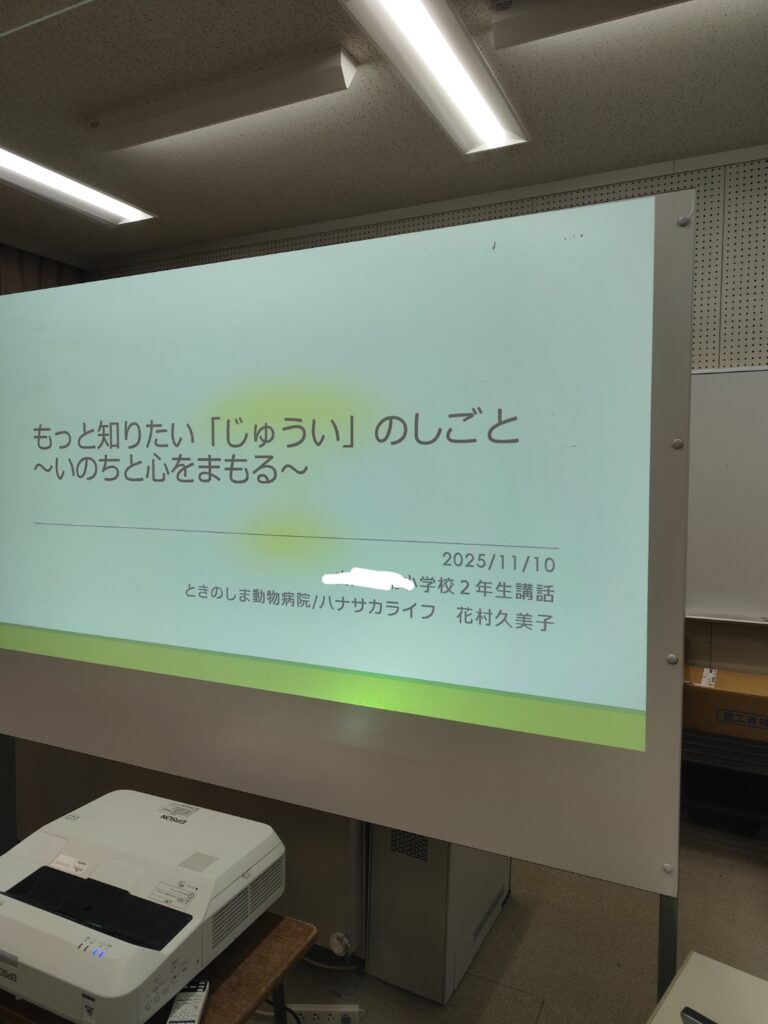
「どうしてかな?」「何ができるかな?」を考える仕事
獣医師というと私のように「動物病院で動物の診察をする人」というイメージがあると思います。
でも実際は微生物から生態系まで専門的に扱う職種。
より身近なところでは私たちの食の安全や防疫にも関わっています。
どの分野でも共通していえるのは、目に見える・見えない困りごとに「どうしてかな?」一つひとつ調べて、答えを見つける仕事だということ。
それにより動物と私たち人が安心して暮らせるようにしているのです。
実際に動物病院で診療した犬猫の紹介場面では、「このコはなんでこうなったんだと思う?」という問いかけに、子どもたちは次々と意見を発表してくれました。
なかでも誤食してしまった症例の画像では、「えーっ?!」という驚きの声が大きくあがりました。
でも、そんな事故も、環境を整えて防ぐことができると伝えると、子どもたちが自分でもできることだ!と気づいてくれていました。
お話の最後には、子どもたちに伝えました。
「どうぶつの困りごとを見てどうしてかな?と考えることは、じつは友だちやまわりの人にもできることなんだよ。」
自分と違う立場の動物への思いやりは、人との関わりにも通じること。
違いを知る・認める・考える・行動するという意識を、獣医師の仕事をきっかけにもってもらえたらという気持ちをこめてお話しました。

終始キラキラしたまなざしを向けてくれた120名の2年生たち。
元気にハイタッチを交わしてくれるその姿に、私もあらためてこの職業の責任を感じたのでした。

獣医師 ・ライフオーガナイザーとして伝えたいこと
動物の行動診療に携わる獣医師として、そしてライフオーガナイザーとして環境をととのえる力を伝える活動をしています。
動物が健康でいられることも、人が安心して暮らせることも、その土台は「環境づくり」にあります。
教育の現場で、子どもたちと考える力や思いやりについて話すこと。
それは、どうぶつの福祉だけでなく、人と動物がともに心地よく暮らせる社会づくりにつながると感じています。
小学校・中学校などへの講師依頼も承っています。
詳しくはお問い合わせフォームからご連絡ください。
公式LINEアカウントからもお問合せいただけます。

獣医師・ライフオーガナイザー®。犬猫と人が安心して暮らせる住まいを整える専門家。獣医師としての行動学の知見を活かし、暮らしと空間の「しくみづくり」をサポートしています。江南市を拠点に、訪問・オンラインで対応中。
公式サイト:ハナサカライフ
