月イチで開催されるCLOプログラム受講メンバーの勉強会に参加しました。
片づけと認知行動療法
勉強会でとりあげるテーマはメンバーリクエストによるものが多いです。
今回は「認知行動療法」について。
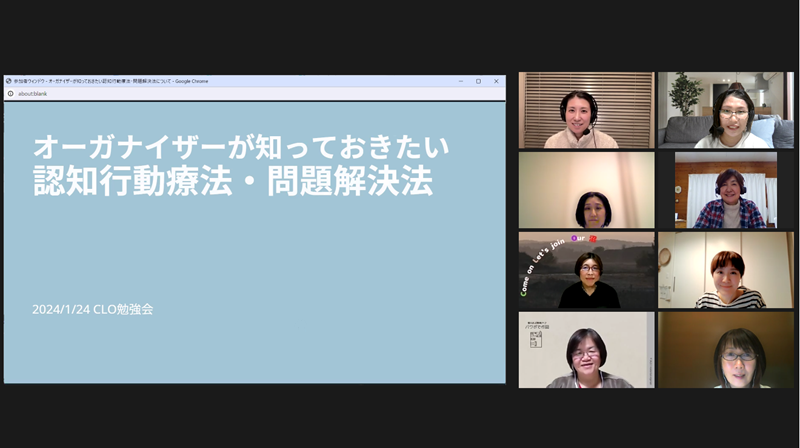
余計な情報を発するわたしの背景はさておき。
認知行動療法とは、ストレスの問題を認知と行動の工夫を通じて自己改善するための考え方と方法のこと。
そのための手段として問題解決法や認知再構成法などがあります。
ちかごろよく聞くマインドフルネスなんかもこれに含まれます。
認知行動療法自体はストレスに対するマネジメントとして、カウンセラーやセラピストなど心理の専門家が提供するものです。
わたしたちがCLOプログラムで学ぶ慢性的に片づけられない方へのサポートにも、心理面の支援が望まれる場合があります。
ライフオーガナイザーはセラピストではないので、認知行動療法をクライアントさんに提供することはありません。
だからこそ知っておきたい点や、意識しておきたいバウンダリー(境界)について話し合いました。
さあ、どんな方法でやってみようか?
なにか問題に直面したとき、「困った…」とフリーズしてしまうことはありませんか?
何を隠そうわたしがそうでした。
問題は解決したいし、そのための方法は思いつく。
なのに「うまくいかないかも」と心配になり、結局踏み出せないことを以前よく経験していました。
ライフオーガナイザーとなってからは「もういい!やっちゃえ!!」と目をつぶって飛び込むことを自分に課していますが、それも心臓に悪い。
認知行動療法の手法のひとつである問題解決法では、問題解決のために役立つ考え方を習得することになります。
なかでも「どうしよう?」ではなく「どうしたらいいかな?」と解決に向けて前向きに捉えてみる、というのがわたしには刺さりました。
闇雲に飛び込むのでなく、小分けにした問題に対してどんなことができるか具体的に出してみる。
それにより漠然と「うまくいかないかも」と心配することが減ります。
試してみることで、その結果から貴重なフィードバックを得ることができます。
それが問題解決の原動力にもなっていくんですね。
実践することで、なんだか根拠のあるポジティブさが身についてきた感じがします。
自動思考に気づいて片づけのストレスを減らす
片づけにおいて自然に浮かぶ考え=自動思考が片づけの妨げになっている場合があります。
「片づけてもどうせまた散らかる」
「わたしが片づけてもどうせ家族が片づけないだろう」
「片づけられないのは恥ずかしい」
などなど。
こうした自動思考をとらえるとそれぞれに対する対処が可能になるので、少しずつ片づけのストレスを減らすこともできます。
前述のとおりライフオーガナイザーが認知行動療法を提供することはできませんが、「こんなのがあるんですよ」とお伝えすることはできます。
知識として取り入れることと、自分の認知を俯瞰してみることを今後も続けていきたいと思います。

獣医師・ライフオーガナイザー®。犬猫と人が安心して暮らせる住まいを整える専門家。獣医師としての行動学の知見を活かし、暮らしと空間の「しくみづくり」をサポートしています。江南市を拠点に、訪問・オンラインで対応中。
公式サイト:ハナサカライフ
